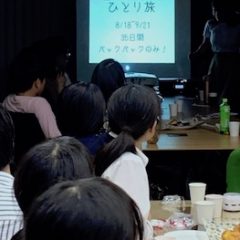ば 高校部(高の原に再統合)
※学研校高校部は高の原校に統合されました。
2025年4月 新高1生を限定募集をします。
面談お申し込みの場合、まずは下記を読んでいただき、ba@suri-gengo-ba.com
にご連絡をください。
メールには、
①お子様の名前ふりがな
②4月からの学校、学年
③ご連絡先電話番号
を記載してください。
□【ば 高校部のご紹
少子化
それに
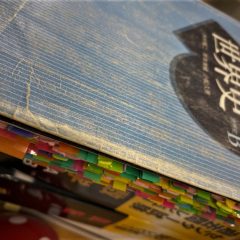
今時は
いわゆ
したが
予備校との違いということでいえば、予備校では一般的にその教科内容を効率的に(時に面白おかしく)教えますが、うちの教室では内容と同時に学習の仕方やそこに向かう姿勢も重視し、それを自然に習得してもらうことにも関わっていきます。こういった方式は、(数として元々少ない)高校生向けの塾との比較でも珍しいことだと思います。
これは
高校で
この状
かといって、その解決のため、高校でまたも依存学習をするのでしょうか?大学入学後にはもはや塾はありません。さらに社会に出たあとも誰かに常に補助してもらうわけにはいきません。基本的には自力で学習をしなくてはならないという日が必ずくると思います。そこへの準備をする、というのも、この高校時代における重要な学びだと私は考えています。そのためにも、大学入学後の完全自立へのつなぎを意識して、ただその場限りで成績を取り繕うのではなく、自分自身で積み上げた力で達成できるように導くというのが、この教室での支え方になります。
これは
さらに
それを
それぞ
*************************************************************************************************
※学研校高校部は高の原に統合されました。ba@suri-gengo-ba.com
◆2025年 3月開始予定 新年度新高1生講座ご案内 ◆
高校受験が続いています。
すでに合格が確定した方はおめでとうございます。
これから本番を迎える方は、今持っている力をなんとか発揮してきてください。うまくいきますように。
4月からはいよいよ高校生です。その高校生たちですが、高校生活になかなか苦戦しています。
学習、特に数学はその本格内容に苦労しますし、いまどきの時代や青年たちの気質に合わない管理手法に対し、心理的なしんどさを感じるケースが相当に増えています。進級の苦労や不登校、中退といった例も珍しくありません。このあたり親の世代の高校時代とはずいぶん変わってしまいました。
一方で大学入試自体は、選ばなければほぼどこかには行けるようになりました。少子化の中、大学も早期確保を目指し、指定校や、各種推薦入試なども増えています。どこかに行ければいいということであれば、あるいはどこどこ大学入学という学歴の取得が目標ということであれば、かなり容易にはなりました。無料やほぼ無料の動画授業の質も上がっています。その意味では費用をかけずに目標達成することも可能です。実にいい時代になりました。
しかし一部の難関大学の難易度は相変わらず高いままです。入試問題の水準も下がりません。この種の入試を突破しようとすれば、相当な努力の積み重ねと、高度な知識や思考の習得が必須になっています。その意味で、同じ大学生という立場でも、そこに至る過程は、まったくの別世界になっています。本格受験組は、狭き門を突破する競争でもあるのと同時に、大学以降も学びは続く(そのあとには就職で選抜を受ける)のでそれに見合う準備は当然必要と考えての選択であるともいえます。
どこに価値をおくかは、本人や家庭の考え方次第です。どれが正しいということはありません。
ただ本格入試の場合、それに対する相応の備えというのがありますし、コツもあります。
特に重要な時期というのも何箇所かあります。そのひとつが、入学までのいまになります。
中学最後の生活をたのしみながらも、ここでどのような準備をして、高校デビューするか。そこをうまく整えるのがポイントです。
高校部では以下のような見取り図と方針で、まずはここをサポートします。
(それに続いて入学後は、高校生としての学びに対応できるように、これまでのやりかたを全面的にやりなおしていきます。
これはそう簡単にうまくいきません。中学までについてしまった依存型の学習の癖を転換するには、少なくとも半年単位の時間が必要です。
ゆるんだりだらけたりで、順調にいかないことも多く、山あり谷ありが続きます。加えてまさに高校時代は青年特有の悩みも増えていきます。)
この難しい3年間、ただ単純に学習補助というだけではなく、それぞれの青年の将来を考え、苦悩を支え、大事にし、付き添っていきます。
まずは高校生活を順調に開始し、生活にも慣れていき、半年後くらいに、いま高校生活が楽しい、この高校に入ってよかったと感じられること。そのための以下の段取りです。
◇「いまどう過ごすかが高校デビューを決める」
受かったのでしばらく勉強はしないでおこうと考える人は多いですが、逆にこのタイミングこそ、準備をしておくべきときです。高校入試対策でそれなりについた学習習慣が壊れる前に少しずつでも始めておきましょう。そうすれば比較的ラクに、スムーズに高校生活を開始できます。
ここから3月を経て4月の高校デビューの仕方はかなり重要になります。
どうしてでしょうか。
◇「同じ実力の者の競争」
まず同じ入試で選抜されていますから、同じ高校の入学者はほぼ互角の実力です。入学後に、やはりこの者たちの中でも順番が振られるので、いままで公立中学で取ったことのないような下の順位となる場合も出てきます。(もちろん最下位も必ずいるわけです。)心の準備なく入ってこれに驚く人が毎年出ます。下位に低迷すると毎日の授業や試験や課題がどれも重荷になってきます。一度「周回遅れ」の立場になってから追いつくしんどさは想像通りなかなかのものです。できればこれはなんとか避けたいところです。(ただしそうなったとしても、それはそれで打開方法はありますが。)
◇「無理なく先取り学習をして、好循環を目指すのは大事」
同様に、授業内容が初見のものになり、ペースもその集団での中位少し上あたりに合わせてきますので、実力が下位の場合、授業についていけなくなるケースが出てきます。これは目立たないですが、英数主要科目(特に数学)において、かなり大きな要素になります。実は中学時代に英数については、塾などですでに先取り学習をしていたので、授業で初めてきくことがほとんどなく余裕できけていたはずです。ところがそれは意識的にやっていたのではなく、なんとなく塾のカリキュラムにのっていたら、そうなっていたという人が大半だと思います。したがって、ここから何も準備せずに受けてしまうと、毎回の授業内容がほとんどわからないといったことも起きます。しかも人生初なのでなにが起きているかが最初うまくわかりません。事態が悪化してようやく気づくまで半年以上かかるということも少なくありません。
そうならないためには、できるだけ無理なく先取り学習をしておくのがコツです。中学のように授業が復習になるようにする。この好循環がうまくできればそんなに苦しむこともないはずです。
◇「高校生活を楽しむためには、ちょっと準備しておくのががポイント。」
その準備は独力でやるのも可能です。しかしやはり助力やアドバイスがある方がなにかと有利です。高校部ではベテランから優秀な若手までずらりそろえました。最難関大の本格受験にも対応できます。しかもみな穏やかで、それぞれ人生経験も豊富です。
ゆくゆくは高度な内容も対応できますが、しかしまずは最初は初心者向けに丁寧にいく予定です。
スタートダッシュにしくじらないようにするために、正式開講も3月からです。もっと早めに決まった場合は、その前から各自準備を開始し、入学後に備えることも可能です。合格者には、何から始めるかの相談も受けます。合格の余韻にひたり、中学最後の生活も楽しみながらも、同時に無理なく4月以降、新しい生活にも備えましょう。
◇新高1生対象に設置する予定の講座のご案内をします。
概要は次のようになります。
****************************
【ば高校部 新高1対象講座】(対面授業)
★授業では小中部同様にiPad+pencil+goodnotesアプリを使用します。これを利用して、各自の手元を見ながらきめ細かく指導していきます。★(持っていない方は4月中を目処に準備してください。)
①開始日:3/12(水)
②時間割:お問い合わせください。
③授業料:お問い合わせください。
④対象生:国公立大学など本格受験をする予定の人。
※指定校入試や推薦入試などの受験希望の場合は定期試験対策が中心になるので、個別指導専用塾をお勧めしています。
※部活中心で高校生活を考えている人も本格受験との両立のためにも調整のしやすい個別指導専用塾をお勧めします。
⑤定員:あり。少人数で行います。定員に達し次第締め切ります。
※規定人数に達しない場合は当該学年開講見送りの可能性があります。
⑥高校部受講条件:あり。
◆【基本方針】高校段階では、みな同じ進度の一斉授業ではなく個別指導の方が合っているケースが現実的には半数以上あると思います。
在籍する学校の授業進度がかなり遅いし水準も低めに設定してある。部活を中心で過ごすのでその空き時間(と余った体力)で受けられる範囲で授業を組みたい。学校によって異なる定期試験対策や課題提出を中学まで同様優先的に考えたい。
こういった場合、うちの教室に限らず、予備校も含めて、一斉方式授業は合いません。無理に参加するとただ座っているだけといった状態になってしまいます。 結果的に進む大学が塾に通わなくても入れたところということにもなります。これは安くはない授業料には‘見合わない’のではないかと思われます。そのうえで、本人にとってもご家庭にとっても何が最適か。このあたりを含めて判断をさせていただいています。
また当教室は小中もごく小規模ですが、高校部はさらに少人数でやっており、事実上個人塾と呼べる規模です。ひとりひとり目が届くようにと、受ける人数も対象も限定しており、授業科目の設定も一部に限られています。また受験情報もどうしても大手の方が、豊富にはなります。大手業者のようにはなかなかいきません。そのあたりを重々ご理解いただいたうえで、高校生に対する上記のうちの方式と他とを十分に比較検討してお申し込みください。
・受講ご希望の場合、まずは面談をさせていただき、教室の内容をご説明します。進学校や中学までの状況、進路希望なども合わせて入塾可否を判断します。なお受講が決まった場合、希望があれば正式授業前から数学を中心に高校準備を各自始めます。これをやっておくと、高校入学後にずいぶん余裕をもって授業を受けることができます。合格旅行や、中学最後の生活を楽しみながらも、あまり無理なく備えておきましょう。
・なお試験前のみの自習利用や、質問のみなどの形式は受けていません。そういうケースは個別指導専門の塾で自習体制の整っている規模のところをお勧めしています。また自力で進むことができる場合は、学校の自習室はもちろん、京都駅などにある有料契約自習室を試してみるという手段もあります。
⑧学習アドバイス:
いずれも希望により受験学習指導プロによる各自に応じたケア付き。具体的には数学を中心にした学習計画サポート、宿題習得度合いやペースの相談および習得度合いのチェックなど。必要に応じた細かい学力特性判断、具体的アドバイスなども行います。
これはこの教室の特徴になります。高校生対象の学習場所はいろいろありますが、予備校では細かい個別状況対応は難しいですし、個別指導はそれを担うのは指導経験のあまりない大学生であることが多いのが一般的です。長年の指導経験ときめ細かなサポートを両立し、加えて教科内容指導も含めて対応するということになります。
ただし小学生の学習のような横について丸付けを全部行うということではありません。(そのようなことを高校生に対しすべきでもありません。)ゆくゆく自律的に学習をするための助走部分の手助けをするということです。大学入学後も将来を考えても、自律的に進められる力がつくかどうかは一番の核心ですし、どのみちそれなしでは難関大に受かることはありません。ここは重要なポイントになります。
以上、ご検討のうえ、お気軽にご連絡をください。
◆◆特集:2020年実施 発展総合探求講座案内◆◆(過去講座)
*************************************
当教室では昨年度、主に小学生向けに、「総合探求講座」を開講し、一年間様々な知やものごとに触れてきました。
今年度は、中高生向けに、さらに本格内容にした「発展総合探求講座」を開講します。
案内人は、理系(数学、サイエンス、プログラミング、生物全般特に野鳥・・)も文系(文学、美術、哲学、歴史、音楽・・)もフルマラソンまでもこなす、山西です。
このまま、中高で漫然と過ごしていても、力がつかないということに気づいた人はこの機会を逃さず、ぜひ受講してください。
***********************************************
★めざすもの
●1●ipadやパソコンを使いこなそう!
今後、社会に出たときはもちろん、大学入学以降はこのあたりのIT機器を使いこなすことがすべての前提になります。小中高でも使用し始めている学校が増えていますが、いまだに昭和方式でのみ行っている学校もまだ多い。しかし学校側の事情に付き合う必要はないと思います。せっかくの21世紀のIT環境なのに、スマホゲームやLINEばかり使ってないで、学習や学び一般でこそ本格的に使用するべきです。その方法を伝授しま
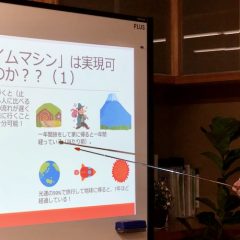
す。これが身につけば、受験学習においても効率が良くなるはずです。
授業では、iPadかpcかmacを準備してください。
●2●すわって黒板をながめていれば「勉強」だ、という思い込みから解放されよう!
学校授業で連日淡々と続く単なる断片知識の一方的注入にはうんざりすると思います。実際にあんなに長時間教室で座っているのに、ほとんど力になっていないということを痛感していると思います。
21世紀の社会に出ていく
キミたちにとって必要なのは、こんな検索すれば出てくる断片用語の受け身での聞き流しではないはずです。
そうではなく、その知識の調べ方、そこからの必要な情報の選び方、そのための読み取り方、戦略的定着のさせかた、そしてすべての背景となる考え方(ものの見方)といったものの習得こそが重要なはずです。(そこに気持ちが向けられるというのが、実は何よりも重要。学ぶことは「損」だから基本的になるべく最低限ですませたい、という種類の大人からは、このような姿勢は決して学べないと思います。)
この授業では、その考えのもとで、より実践的で本質的なことを、ともに興味を持
って、学びます。その方が何倍も愉しいし、身にもつ
き、能力も上がっていきます。その方法で学習にも取り組めば、「成績」といったものも伸びていくはずです。
************************************
★なにをする?(ほんの一部紹介。)
●1●「読む」
メインテキストを定めて、
実際に読みながら、読
み方を含めて伝授します。
メインテキストは、話題の本。この本はおもしろい。一生ものになります。(最後に載せるAmazonの書評を読んでみてください。)
『ビッグヒストリーわれわれはどこから来て、どこへ行くのか宇宙開闢から138億年の「人間」史』
(デヴィッド・クリスチャン、シンシア・ストークス・ブラウン、クレイグ・ベンジャミン著、明石書店)
それ以外にもたくさんの本
を使っていきます。絵本や漫画以外、一冊もまともに読んだ本が無いような水準のまま、大学生になっても、本格的な学問はできません。表面的短文情報の氾濫するいまだからこそ、きちんと読むこ
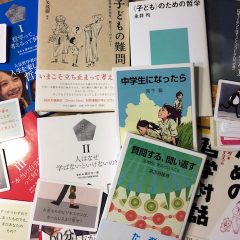
とは重要さを増しています。国語の問題文以外でまともに文章も読んだことがないという人は、ここが読むチャンスです。
●2●「プログラミングする」
文理問わず今後必須知識になるプログラミング講座も季節講座で入れていきます。
このあとの世代は小中か
ら学校で本格的に学んでいきますが、キミたちの世代はまだそこから抜けてしまっています。今後、社会に出て、下の世代から教えてもらうしかないIT難民になるのではなく、まだしも頭の柔らかいいまのうちに習得してしまおう。
ここでは、単なる、機械の

操作言語としてではなく、アルゴリズムといったものの、その発想方法も含めて知ることを重視していきます。Pythonを基本としながら、Excelなども積極的に使っていく予定です。
●3●「問う」
たとえば「問う」ことについて。
学生の立場で、常に問いを出され、頭をひねってなんとかその答えをひねり出す、という訓練を小さい時から繰り返してきたと思います。しかし問うことそのものについて考えたり、正面から自分で作ったという経験は少ないでしょう。
問うとは何か。問い、には、「閉じた問い」と、「開いた問い」に分けることができます。
「いくつですか?」「15歳です」、といったように、はい、いいえなど限定的に答えられるのが、閉じた問い。
「いまどんな気持ち?」のように、自由にいろいろな答えが返ってくるのが、開いた問い、です。
前者は、答えやすい、誰にでもできる、短時間で情報を集められる、という一方で、会話のキャッチボールができない、事務的表面的に
なりやすいといった面もあります。
後者は、自分の気持ちや考えを自由に表現できる、奥まで知ることでより深い情報が得られる一方で、答えにくい、焦点が合わせにくい、会話の技術が必要といった両面があります。
さて自分はこれについてどのように問いを立てることができるのか。その問いはどちらであるのか。
実際に作ってみる中で、そういったことも含めて、自覚的に学びます。
***********************************************************
◆使用予定アプリ一部紹介
〇調査:ウィキペディア、google earth、google arts & culture 、辞書類
〇整理:メモ、Pages、Numbers、Evernote (高校生)Excel
〇発表:Keynote
〇学習管理&連絡:メッセージ
〇プログラミング言語:pythonista
***********************************************************
※Amazonの書評『ビッグヒストリーわれわれはどこから来て、どこへ行くのか』
★考え方・生き方がガラリと変わる歴史書★
「本書では、重要な歴史のとらえ方として、宇宙開闢(かいびゃく)からの歴史を複雑さを増す過程だとしている。
しかし、「複雑さの度合が高い=高級である」とかそういう話ではない。
著者のD・クリスチャンがTEDプレゼンテーションでも説明していたが、複雑さが増すということは、脆(もろ)さが増すということでもある。現在の人間、現在の人間社会は何と脆いことか。それゆえに、私たち人間は、未来について、また、いま直面する課題について、協働して知恵を働かせるべきときなのである。
そのことを意識しながら読むと、自分の日々の生活、一つ一つの行動が世の中のいろいろなこととつながってくる。
数千年後の子孫に誇れるような社会にしなくてはいけない。(孫の世代に、とかいうのは短すぎる)
また人間だけのことを考えるのではなく、生物圏全体の中で他の生物や環境のことも考えなければいけない。
わたしは、人間はもう争い(戦争)などせずに協調していけると信じたい。真の意味で他の生物たちとも共存・共生できると信じたい。138億年という時間を俯瞰(ふかん)することで、あらゆる差が相対化されて無に近づく。
わたしはこの本は、あらゆる差別や格差の拡大などに反対する本でもあると思う。
最初の数章は自然科学の話が続くのでサイエンスの本と思う人もいるみたいだが、これは歴史の本である。
もちろん、人間社会の歴史も丁寧に描かれている、というか、全13章のうち5章以降は人間および人間社会について述べている。
原初の社会については権力の起源にも迫っていて面白い。ここで、「合意性権力」や「強制的権力」などの概念も出てくる。
佐藤優氏の帯文にあった「この本を読む前と読む後では世界の見方が変わる」というのは本当だった。
わたしにも世界観の変化のようなものが訪れつつある。
なお、日本語版監修の長沼毅氏が本書について解説した「ビッグヒストリーを味わい尽くすために」という動画がyoutubeにアップされている。本を読むうえでもとても参考になったので、まだご覧になっていない方にはぜひ視聴をお薦めしたい。
ノブ様(一部略)」
***********************************************************